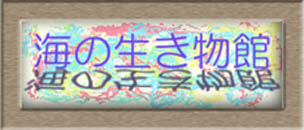
海辺の生き物の世界へようこそ

私たちの大学は、瀬戸内海に面したところにあります。ここは、比較的海になじみやすい環境です。
2回生前期に行われる臨海実習では、海辺の生物の観察法や分類の勉強をします。
みなさんも、海に行ったときなど、いろいろな生き物を見かけることがあると思います。
カニとか、魚とか、貝だとか、わかりやすい生き物も多いです。
でも、中には「これなに?、生き物??・・・」なんてこともあるのではないでしょうか。
そんな疑問の解決にこのページが、お役に立てれば幸いです。
難しいことは抜きにして、写真だけでもお楽しみください。
2008年4月30日更新

海綿動物(Prorifera)
昔は、スポンジの材料でした。今では、合成のスポンジにその名を奪われていますが、こっちが元祖スポンジです。
刺胞動物(Cnidaria)
刺胞という、仕込み針を使って、獲物をとらえます。
扁形動物(Platyhelminthes)
平べったい形をしています。再生の実験で有名な、プラナリアの仲間です。
紐形動物(Nemertinea)
文字通り、紐のような形をしています。
軟体動物(Mollusca)
海辺で見かける動物、ナンバーワン。いろいろあります。
多板類:小さな貝殻がたくさん連なっている仲間です。
腹足類:色々な形をしていますが、みんな1枚の貝殻を持つ仲間です。
斧足類:2枚貝です。
環形動物(Annelide)
管状の体をしています。節があったり、足があったり、触手があったり、もう、うにゃうにゃです。
ゆむし動物(Echiura)
釣りの餌に使われる、好餌のことです。
星口動物(Sipuncula)
口の周りに、触手が星状に配置することから、この名前が付きました。
節足動物(Arthropoda)
エビ・カニの仲間です。でも、似てもにつかないモノも同じ仲間に入っています。
棘皮動物(Echinodermata)
クモヒトデ、ヒトデ、ウニ、ナマコ、外見は似ていませんが、外表面に小さなトゲトゲがある仲間です。
原索動物(Protochordata)
食用になるモノもあります。 岩にくっついていますが、植物ではありません。
その他


